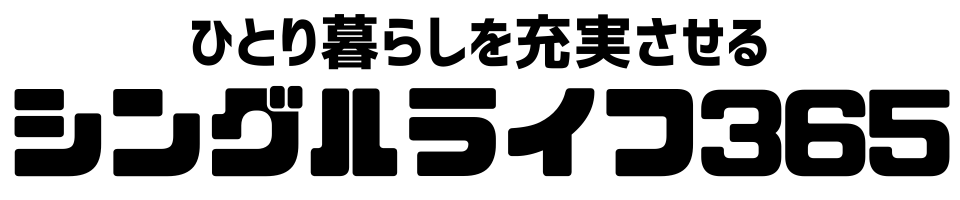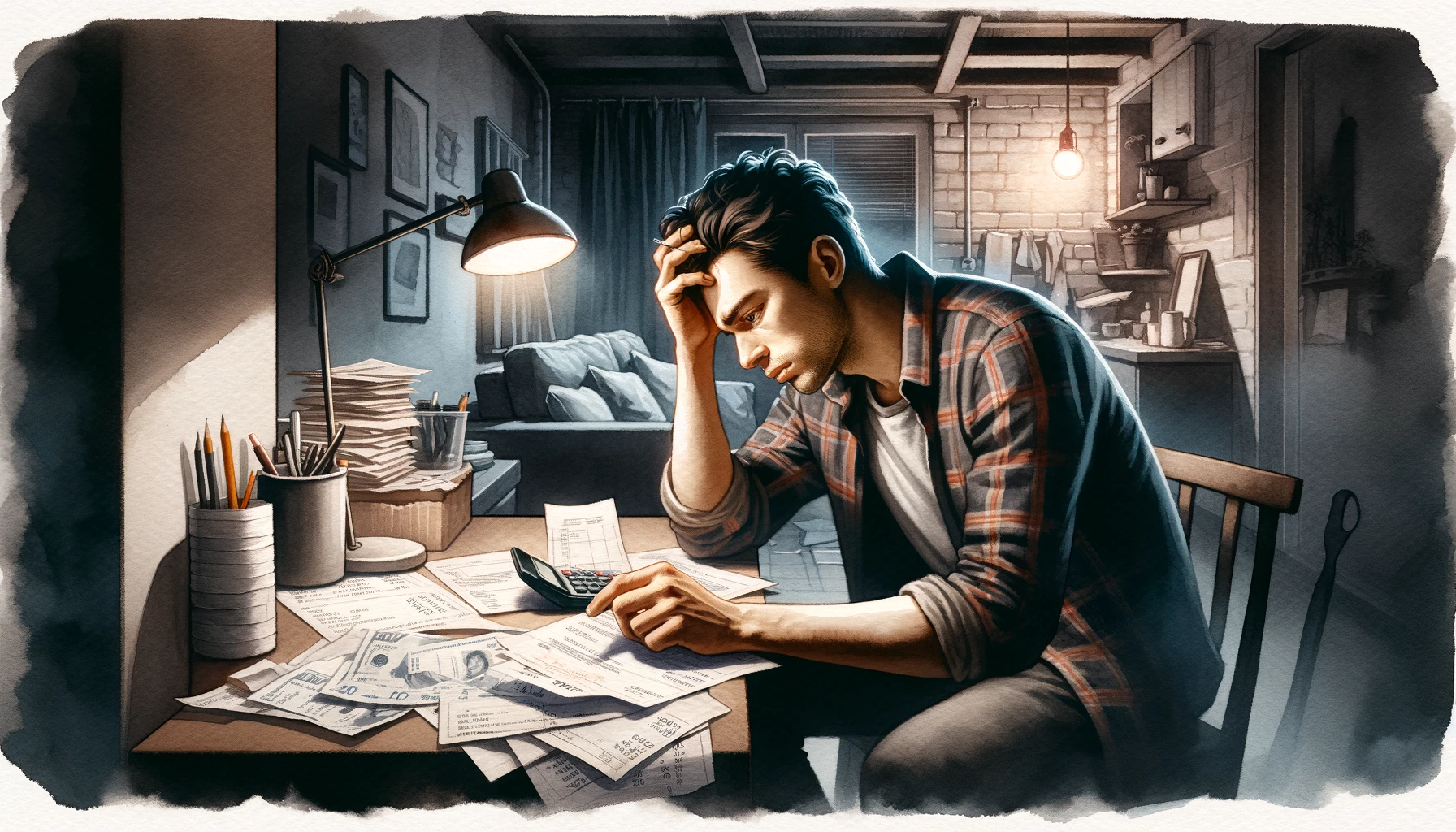「一人暮らしがしたいけどお金がない」と悩んでいる方の中には、大学生、社会人、フリーター、あるいは女性特有の事情を抱えた方も少なくありません。
実際、貯金無しで始めることに不安を感じるのは当然のことです。
しかし、経済的に厳しい状況でも、一人暮らしを実現するための方法や支援制度は数多く存在します。
この記事では、「一人暮らしがしたいけどお金がない」と悩んでいるすべての人に向けて、初期費用の目安や節約術、行政や自治体の支援制度など、現実的かつ実践的な情報をわかりやすく紹介していきます。
- 一人暮らしに必要な初期費用と生活費の目安
- 初期費用を抑える物件や制度の探し方
- 支援制度や補助金の活用方法を理解できる
- お金がない状況でも現実的に一人暮らしを始める方法
一人暮らしがしたいけどお金がない時の対処法

- 一人暮らしで必要な費用の目安
- 初期費用ゼロでも始められる?
- 貯金無しで始める際の注意点
- 一人暮らし支援制度の活用
- 家賃を抑える部屋探しのコツ
- 食費・光熱費の見直しと節約
- 副業を取り入れて生活費を補う
一人暮らしで必要な費用の目安

- 初期費用と毎月の生活費が必要
- 初期費用の相場は、家賃の4~6ヵ月分
- 毎月の生活費は家賃を含めて17万円前後
初期費用と毎月の生活費が必要
このように言うと不安になるかもしれませんが、一人暮らしを始めるにはある程度の初期費用と毎月の生活費が必要です。
特に初めての一人暮らしであれば、何にどのくらいお金がかかるのか見当がつかず、戸惑う人も少なくありません。
主に敷金・礼金・仲介手数料といった初期費用に加えて、家賃・光熱費・食費・通信費などが継続的にかかってくるのが一般的です。
初期費用の相場は、家賃の4~6ヵ月分
一人暮らしの初期費用の相場は、家賃の4~6ヵ月分だといわれています。
例えば、都内で一人暮らしを始める場合、初期費用は30万〜50万円ほどを見込んでおきましょう。
これには引越し代や新たに購入する家具・家電の費用なども含まれることが多いため、予算に余裕を持って準備する必要があります。
毎月の生活費は家賃を含めて17万円前後
また、毎月の生活費については、家賃が5〜6万円、食費や光熱費・日用品費などを含めると、合計で17万円前後かかるケースが一般的です。
これらの出費を事前に具体的に把握しておくことで、自分にとって無理のない家計プランを立てることができ、計画的な準備や資金調達がしやすくなります。
さらに、出費の中で削れるポイントや、費用を抑える方法についても併せてリサーチしておくと、より安心して一人暮らしをスタートさせることができるでしょう。
初期費用ゼロでも始められる?

- 初期費用ゼロ」や「敷金・礼金不要」は増えている
- 何かしらの条件がつくのが一般的
- 長期的にみると割高になるケースも多い
「初期費用ゼロ」や「敷金・礼金不要」は増えている
もし初期費用を準備できない場合でも、工夫と情報収集をしっかり行えば、一人暮らしを始めることは十分に可能です。
最近では「初期費用ゼロ」や「敷金・礼金不要」をうたう賃貸物件が増えており、初期負担を抑えたい人にとっては心強い選択肢となっています。
何かしらの条件がつくのが一般的
これらの物件では、保証会社を利用することが条件となっていたり、家賃に敷金・礼金相当分を上乗せして毎月の支払いに含める形式が一般的です。
また、不動産会社によっては、家具家電付きで初期費用をほぼゼロに抑えられるキャンペーンを実施していることもあります。
長期的にみると割高になるケースも多い
とはいえ、その分月々の家賃が相場より高く設定されているケースも多いため、契約前に支払総額をしっかりと確認し、長期的な支払い計画を立てることが重要です。
短期的には助かる制度でも、数年単位で見ると割高になる場合があるため、ライフプランに合わせた選択を意識しましょう。
貯金無しで始める際の注意点

- 無計画にスタートすると後々困ることに
- 最初の1〜2ヶ月間は予想以上にお金が必要
- リボ払いや分割払いは生活のゆとりを失う原因
- たとえ少額でも緊急用資金を用意しておくと安心
無計画にスタートすると後々困ることに
たとえ貯金が無くても一人暮らしを始めることは可能ですが、無計画にスタートすると後々困ることになりかねません。
そのため、しっかりとした生活設計を立てた上で行動することが求められます。
最初の1〜2ヶ月間は予想以上にお金が必要
貯金がない状態でも無理なく一人暮らしを始めるためには、あらかじめ起こりうる事態を想定し、できる範囲での備えを整えておくことが鍵となります。
特に最初の1〜2ヶ月間は、家賃や引越し費用、家具・家電の購入など出費が一時的に多くなりがちなので、予想以上にお金が必要になるケースが多いです。
リボ払いや分割払いは生活のゆとりを失う原因
このため、クレジットカードで一時的に支払う場面も出てくるかもしれませんが、必要以上の利用には注意しましょう。
リボ払いや分割払いの利用が続くと、利息がかさんで返済負担が重くなり、生活のゆとりを失う原因となります。
なるべく現金で支払える範囲に抑えた生活を心がけることが大切です。
たとえ少額でも緊急用資金を用意しておくと安心
また、急病や家電の故障など、思いがけないトラブルに備えるためにも、最低でも3万〜5万円程度の緊急用資金を用意しておくと安心です。
たとえそれが少額でも、あるのとないのとでは安心感が大きく異なります。
一人暮らし支援制度の活用

- 各自治体には様々な形の制度が整備されている
- 収入が一定以下の人に家賃の一部を補助する制度
- 申請は役所や福祉事務所で行うのが一般的
各自治体には様々な形の制度が整備されている
ここでは、一人暮らしを支える支援制度の使い方について紹介します。
各自治体には、住居確保給付金をはじめ、母子家庭向けの補助や生活困窮者への家賃補助、ひとり親支援、生活保護制度など、さまざまな形の制度が整備されています。
収入が一定以下の人に家賃の一部を補助する制度
中でも住居確保給付金は、収入が一定以下の人に対して家賃の一部を一定期間補助してくれる制度で、多くの人にとって非常に心強い支援となっています。
母子家庭や若年層向けの支援は、地域によって異なる場合があるため、居住予定の自治体に問い合わせてみることが大切です。
申請は役所や福祉事務所で行うのが一般的
例えば、失業中や非正規雇用で収入が少ない場合でも、こうした制度を使えば住居の確保がしやすくなり、安心して生活を始めることができます。
申請は役所や福祉事務所で行うのが一般的ですが、支援制度によってはオンライン申請が可能な場合もあります。
申請時には、本人確認書類や収入証明、賃貸契約書などの必要書類を揃える必要がありますが、事前にチェックリストを確認しておけばスムーズに手続きが進められるでしょう。
家賃を抑える部屋探しのコツ

- 毎月の固定費である家賃は最も大きな負担
- 駅から距離がある場所や築年数が経過した物件
- 1階や北向きの部屋は敬遠されがちでお得
- 条件を明確にして効率的に探すことが大切
毎月の固定費である家賃は最も大きな負担
このように考えると、部屋探しの段階でいかに家賃を抑えるかが、長期的に安定した一人暮らしを実現するための重要な鍵となります。
特にお金に余裕がない場合、毎月の固定費である家賃は最も大きな負担となりやすく、工夫次第で数万円の違いが生まれることも少なくありません。
駅から距離がある場所や築年数が経過した物件
例えば、駅から少し距離がある場所や、築年数が経過した物件を選ぶことで、同じ広さの部屋でも2〜3万円程度家賃を抑えることが可能です。
1階や北向きの部屋は敬遠されがちでお得
さらに、あまり知られていませんが、1階や北向きの部屋は敬遠されがちなため、条件を気にしなければお得な家賃設定になっていることもあります。
条件を明確にして効率的に探すことが大切
その他にも、礼金や更新料が不要な物件を選んだり、数ヶ月間の家賃が無料になるフリーレント付き物件を活用することで、初期費用と月々のコストを同時に抑えることができます。
物件情報サイトや不動産会社では、これらの条件で絞り込み検索が可能な場合も多いため、条件を明確にして効率的に探すことが大切です。
食費・光熱費の見直しと節約

- 食費と光熱費の節約は一人暮らしの生活を支える柱
- 食費はまとめ買いと冷凍保存で食品ロスを減らす
- 光熱費は料金プランの見直しと家電の使い方を工夫
食費と光熱費の節約は一人暮らしの生活を支える柱
このように考えると、食費と光熱費の節約は一人暮らしの生活を支える柱になります。
日々の支出を見直すことで、月単位で見ると数千円から数万円の節約につながることもあります。
食費はまとめ買いと冷凍保存で食品ロスを減らす
例えば、食費を抑える方法としては、安いスーパーを複数チェックして特売日を活用したり、まとめ買いや冷凍保存を取り入れて食品ロスを減らす工夫が有効です。
また、外食を減らし、週に数回でも自炊を行うだけでも食費全体が大きく変わってきます。
光熱費は料金プランの見直しと家電の使い方を工夫
一方、光熱費の節約には、電力会社の料金プランを見直したり、季節に応じた省エネ家電の使い方を工夫することが効果的です。
例えば、夏場や冬場は冷暖房費がかさみやすいため、サーキュレーターや断熱カーテンを使って効率的に室内温度を保つなどの工夫が求められます。
さらに、こまめな電気の消灯や使わない家電のコンセントを抜くことなど、意識次第で日常的な無駄を防ぐことができます。
副業を取り入れて生活費を補う

- 非常に現実的な選択肢のひとつ
- 空き時間を有効に使って収入を得る
- 個々のスキルや興味を生かした業務内容を選べる
- 実績を積み重ねて徐々に収入の柱を太くしていく
非常に現実的な選択肢のひとつ
副業を取り入れて生活費を補うという考え方は、現代において非常に現実的な選択肢のひとつとなっています。
特に、近年ではインターネットを活用した働き方が広まり、誰でも手軽に副業を始めやすくなりました。
空き時間を有効に使って収入を得る
クラウドワークスやココナラといったクラウドソーシングサービス、またはタイムチケットなどのスキルシェアアプリ通じて、空き時間を有効に使って収入を得る方法が注目されています。
これらのサービスはスマートフォン一台あれば始められるものも多く、パソコンを使いこなせなくても取り組みやすい点が大きな魅力です。
個々のスキルや興味を生かした業務内容を選べる
特に、タスク形式の副業であれば、短時間で完結する作業が中心のため、忙しい人でも取り組みやすく、初心者にもハードルが低いのが特徴です。
例えば、文章作成、データ入力、ロゴやイラストの制作、SNS運用のサポートなど、個々のスキルや興味を生かした業務内容を選べる点が、長続きする理由のひとつです。
また、これらの仕事は在宅でできることが多く、通勤時間の節約や柔軟なスケジュール調整が可能になるため、日常生活との両立がしやすくなります。
副業を継続していくことで、経験が積み上がり、クライアントからの信頼度も向上していきます。
実績を積み重ねて徐々に収入の柱を太くしていく
報酬単価は案件によってさまざまですが、実績を重ねることで単価の高い案件を受注できる可能性が広がります。
その結果として、初めは少額でも、長期的に見れば安定した副収入を得られる仕組みを築くことが可能です。
副業を生活の補助とするためには、まずは実績をコツコツと積み重ね、徐々に収入の柱を太くしていくような意識が求められます。
無理のない範囲で継続的に取り組むことで、生活全体の安定にもつながっていくでしょう。
一人暮らしがしたいけどお金がない様々なケース
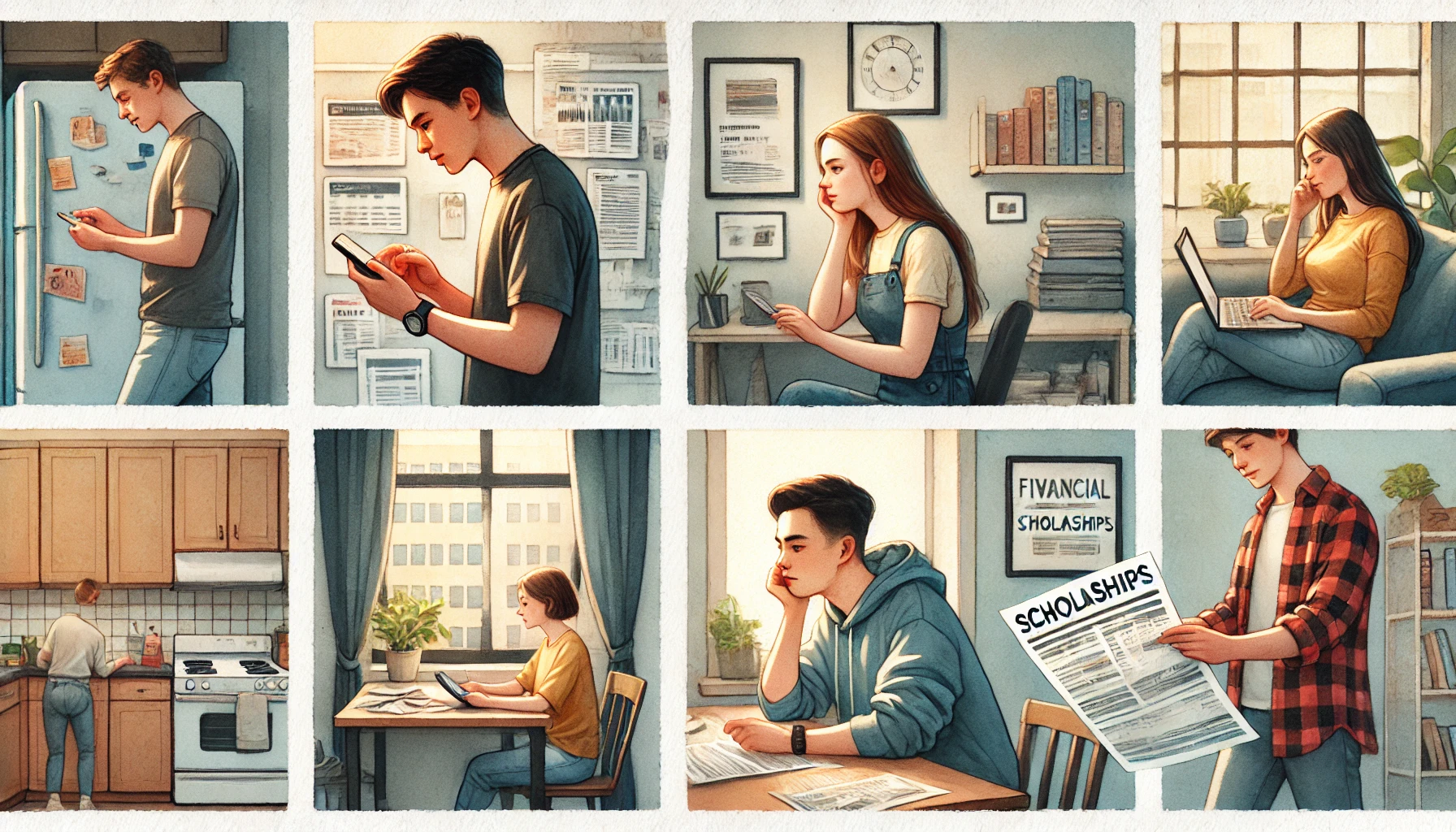
- お金がない大学生の選択肢とは
- フリーターでも一人暮らしできる?
- 社会人でもお金がないと無理?
- お金がない女性でも始められる?
- 実家を出るタイミングの見極め方
お金がない大学生の選択肢とは
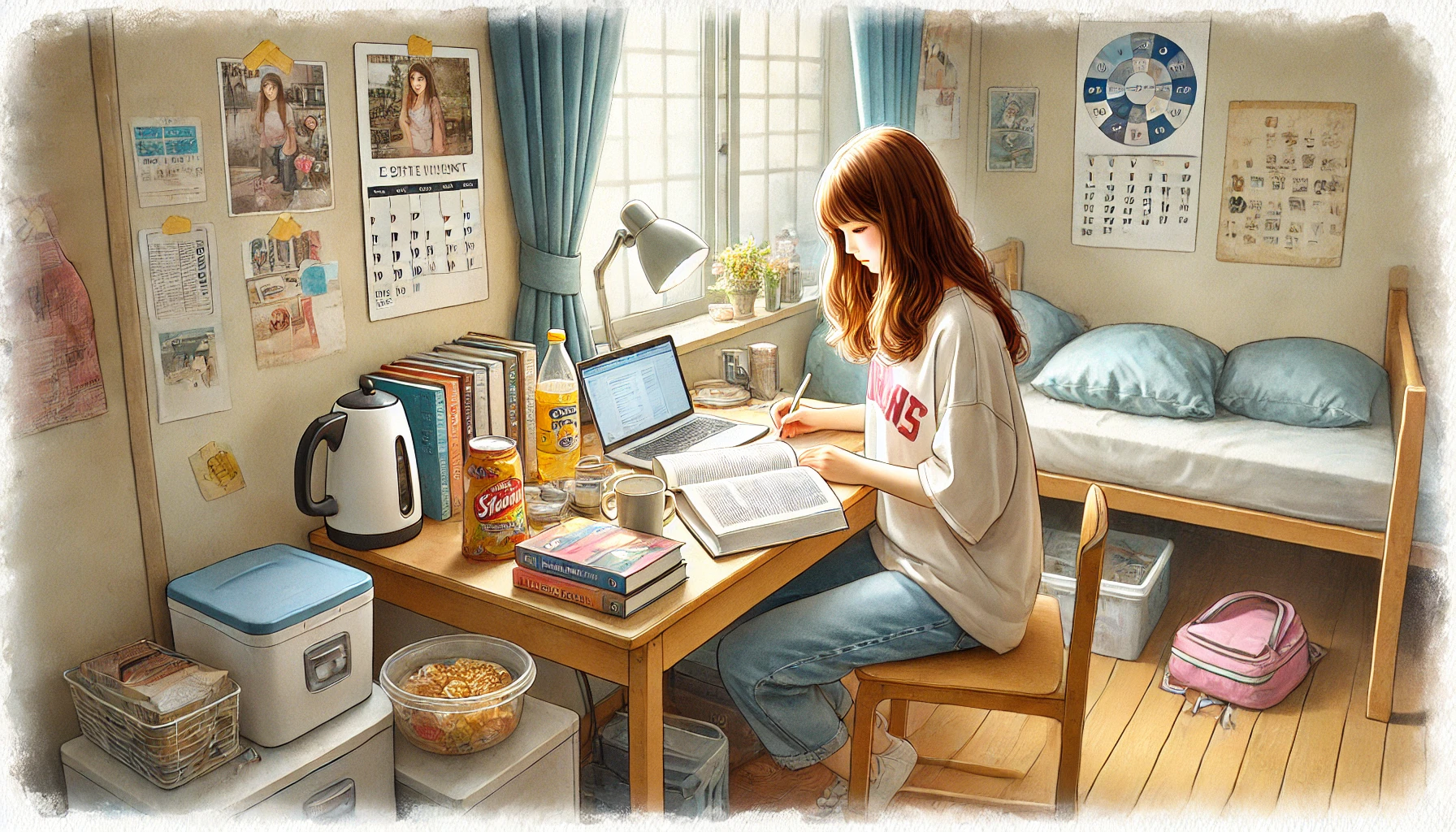
- 学業とバイトの両立には工夫が求められる
- 大学の学生寮や家賃補助制度を活用する
- リサーチは早めに!条件の良い物件はすぐに埋まる
学業とバイトの両立には工夫が求められる
大学生が一人暮らしを始めるには限られた選択肢の中から工夫する必要があります。
なぜなら、アルバイト収入や仕送りだけで生活費をまかなう場合、余裕のある暮らしは難しいからです。
さらに、学業とバイトの両立が必要になるため、時間の使い方にも工夫が求められます。
大学の学生寮や家賃補助制度を活用する
例えば、大学の学生寮や家賃補助制度を活用することで、家賃を大幅に抑えることができます。
学生寮であれば光熱費込みのことも多く、家計管理がしやすいというメリットがあります。
また、大学によっては奨学金とは別に住居に関するサポートを設けている場合もあるため、事前に情報を収集しておくことが大切です。
リサーチは早めに!条件の良い物件はすぐに埋まる
実家から通えない場合は、通学圏内でできるだけ家賃の安いエリアを早めにリサーチしておくことも重要です。
条件の良い物件はすぐに埋まってしまう可能性があるため、時期を見て内見を早めに済ませておくと安心です。
こうして情報と準備をしっかり整えることで、限られた収入の中でも現実的な一人暮らしを実現することができます。
フリーターでも一人暮らしできる?

- 急な出費や予期せぬトラブルに備えるのが課題
- 家賃に関しては「手取りの3割以内」に抑える
- 節約と収入源を複数持って生活の安定性を高める
急な出費や予期せぬトラブルに備えるのが課題
多くはフリーターでも、生活費の内訳を見直し、無駄を省く意識を持てば、限られた収入でも安定した生活を送ることは可能です。
しかしながら、収入が月によって変動することが多く、急な出費や予期せぬトラブル、病気などに備える余裕を持つのが難しいという現実も見逃せません。
家賃に関しては「手取りの3割以内」に抑える
そのため、毎月の生活費にはある程度の余白を持たせておくことが大切です。
例えば、家賃に関しては「手取りの3割以内」に抑えるというルールを自分に課すことで、支出のバランスを取ることがしやすくなります。
節約と収入源を複数持って生活の安定性を高める
さらに、短期のアルバイトや単発の仕事を組み合わせることで、収入源を複数持つ工夫も重要です。
食費や光熱費を節約する具体的な方法も併せて取り入れることで、生活の安定性を高めることができます。
社会人でもお金がないと無理?

- 収入と支出のバランスが崩れていれば難しい
- 社会人でも収入面で不安を抱えている人も少なくない
- お金がない」状況では工夫と計画性が必要
収入と支出のバランスが崩れていれば難しい
これを現実的に見つめると、たとえ正社員であっても収入と支出のバランスが崩れていれば、一人暮らしを安定して続けるのは非常に難しいと言えます。
特に新卒の社会人や、初任給が低めの職場に勤めている場合、家賃や食費、光熱費、通信費など、固定費だけでもかなりの負担となるケースが多いです。
社会人でも収入面で不安を抱えている人も少なくない
さらに、ボーナスが出ない、あるいは年収が想定より低いなど、収入面での不安を抱えながら生活している人も少なくありません。
仮にどれだけ収入があっても、それ以上に支出が多ければ生活は立ち行かなくなるため、自分の生活スタイルを見直し、できる限り無駄を省く努力が必要です。
「お金がない」状況では工夫と計画性が必要
社会人であっても「お金がない」という状況では工夫と計画性が求められます。
例えば、職場の近くに住むことで通勤にかかる交通費や移動時間を節約することができます。
また、外食を減らし、自炊を基本とすることで食費の負担を軽減するのも非常に効果的です。
その他にも、格安スマホに切り替えたり、電力会社のプランを見直したりするなど、日常的な支出の最適化も重要です。
お金がない女性でも始められる?

- 使える制度やサービスを積極的に活用
- 同居人はいるがシェアハウスはメリットも大きい
- 敷金や礼金が不要な物件やフリーレント物件
使える制度やサービスを積極的に活用
家計が厳しい女性であっても、一人暮らしを実現するための方法は、工夫と知識を持つことで数多く見つけることができます。
生活費を削減するためには、支出をしっかり管理し、使える制度やサービスを積極的に活用することが大切です。
特に、公的支援制度や割引制度を正しく理解し、効果的に使うことで、初期費用や毎月の生活費を大幅に抑えることができます。
同居人はいるがシェアハウスはメリットも大きい
たとえば、シェアハウスを選べば、家具や家電があらかじめ設置されているケースが多く、これらを自分で用意する必要がないため、初期投資を大きく減らすことができます。
さらに、同居人と光熱費やインターネット代などの固定費を分担できる点も経済的に助かります。
引っ越しの手間や準備の時間、さらには初期コストも削減することができるでしょう。
- UR都市機構:ルームシェアとは?メリット・デメリットと失敗を防ぐコツ
敷金や礼金が不要な物件やフリーレント物件
加えて、敷金や礼金が不要な物件や、契約から一定期間家賃が無料になるフリーレント物件を選ぶと、入居時の金銭的負担を一層軽減できます。
ただし、すぐに申し込みが入る物件であれば、わざわざ敷金・礼金を不要にする必要もないので、一般的には、入居者が集まりづらい理由があると考えた方がいいでしょう。
このような物件の情報は、不動産情報サイトだけでなく、自治体の住宅支援窓口やNPO団体のサイトなどにも掲載されていることがあり、幅広く情報を集める姿勢が重要になります。
実家を出るタイミングの見極め方

- 環境を変えたいという意欲が強まった時
- 人生の転機は住まいを変える自然なタイミング
- 経済的・精神的な準備の両方が必要
環境を変えたいという意欲が強まった時
ここからは、実家を出る最適なタイミングについて、より深く掘り下げて考えてみましょう。
一般的には、収入が安定し、毎月の生活費を無理なく賄えるようになってから実家を出るのが基本とされています。
しかし、経済的な側面だけでなく、精神的な自立を果たしたいという気持ちや、これまでの環境を変えて新たな生活をスタートさせたいという意欲が強まった時も、大きなきっかけになります。
人生の転機は住まいを変える自然なタイミング
例えば、就職や進学といった人生の転機は、住まいを変える自然なタイミングです。
新しい職場や学校の場所によっては、通勤・通学時間が長くなりすぎることもあり、それを避けるために一人暮らしを決断する人も少なくありません。
また、家族との関係性やプライバシーの問題から、自立した生活を望むケースもあります。
経済的・精神的な準備の両方が必要
ただし、こうした気持ちだけで勢いよく実家を出てしまうのは危険です。
一人暮らしを始める際には、毎月の生活費を正確に見積もり、どの程度の家賃であれば支出を圧迫しないかを確認しておく必要があります。
そのためには、生活費全体をシミュレーションし、必要な準備期間を設けることが重要です。
自分にとってベストなタイミングを見極めるには、経済的・精神的な準備の両方が整っているかをしっかり見つめ直すことが鍵となります。
【まとめ】一人暮らしがしたいけどお金がない時に必要なこと

今回は、「一人暮らしがしたいけどお金がない」と悩んでいるすべての人に向けて、経済的に厳しい状況でも、一人暮らしを実現するための方法や支援制度について、現実的かつ実践的な情報を解説しました。
最後に、この記事のポイントをまとめます。
この記事のまとめ
- 初期費用は家賃の4~6ヵ月分が目安
- 毎月の生活費は家賃込みで約17万円かかる
- 初期費用ゼロ物件もあるが条件を要確認
- 敷金・礼金不要でも月額家賃が高めな傾向
- 家賃を抑えるには駅から遠い物件も選択肢
- 北向き・1階の部屋は安くなる場合がある
- フリーレント物件を活用すると初期費用が減らせる
- 食費はまとめ買いと自炊で節約できる
- 光熱費はプラン見直しと節電習慣が鍵
- 緊急資金として数万円でも用意しておくと安心
- リボ払いや分割払いの使いすぎには注意が必要
- 副業で生活費を補う手段も有効
- 学生は寮や家賃補助制度を活用できる
- 支援制度は自治体により異なるため事前確認が必要
- 精神的・経済的に準備が整ったタイミングで独立を判断する